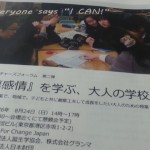他律的な内発的動機付けではなく、「達成感」を持たせることが大事
「行動を開始させ、持続させる過程のこと」これを『動機づけ』
といいますよね。
この動機づけには2つの種類があります。
内発的動機づけ と 外発的動機づけ
ですね。
『内発的動機づけ』とは、自ら湧き起こるやる気。何かを面白いと思う気持ち(知的好奇心)に基づいたもの。一方
『外発的動機づけ』とは、外から与えられる賞罰にもとづいたやる気。です。
子どもにとって、ご褒美をもらうことやほめられることは賞になり、叱られることは罰になります。お皿を洗ったらお小遣いをもらえるから、あるいはお皿を洗わないと怒られるからと、お手伝いをするのは、外発的動機づけによるものと考えられます。
こうみると、子どもたちにも『内発的動機づけ』による行動が理想とは思いますが、まだ自分を律することのできない子どもにとっては大変難しいことです。(正直、大人でも難しいことですが)
以下、学研出版サイトからの引用をまとめました。
特に学力向上を考えると、 「内発的動機付け」だけでは限界があるようです。内発的動機付けの面白い授業だけで終わってしまったら、次はどうするのか?「他の人(教師)に面白い授業をしてもらう」ことに慣れてしまい、結局「受身的」になってしまうからだそうです。このことを教育心理学者の速水敏彦さんは、「内発的動機付けには自律的と他律的がある」(2008年7月児童心理)と指摘してされています。他律的な内発的動機付けでは、「わかる」けれども、いざ問題を解いてみると「できない」という体験になり、モチベーションは下がります。次への意欲を持たせる=自律的な内発的動機付けにするには、 「達成感」を持たせることが重要。
なのだそうです。やっぱりある程度、トレーニング(練習)的な要素は必要なのですね。そこを乗り越えたときに得られる「達成感」。そこをどう、感じさせることができるか? が課題です。
…と、エントレイントメントな話題が、いきなり学童期に入ってしまいましたが、内容が継続的でないことをご容赦ください。
なぜ今回この「動機づけ」をテーマにしたかというと、ほかでもない現在わが子でかなり苦労中。宿題やらずに遊びにいき、アノ手・コノ手でも一時のことで、まったく懲りず、最後は「やらなくてもい~や」的な感じになりかけました。
これ以上は、互いの精神的によくないと、担任に「声はかけますが、本人に任せしばし様子を見ます」と連絡したところ、「君ならやれる!」と声をかけていただいたそうで、俄然やる気になって、今日は昨日の分もすべて終えました。大好きな担任の力はすごい!
親子間での頑張りもほどほどが重要だと思います。いい母をするとすべてわが子へ影響しますので、「助けて~」とか「相談させてください」と言えることも大事だなと痛感します。
問題は「継続」…ですね。日々、試行錯誤ですが…。またレポートします。
わが子にあった方法を日々、模索中~。漢字も一気に増えました!
参考資料:
「乳幼児発達心理学」繁多進ー編著/福村出版
学研出版サイト「教育情報ナビ」内発的動機付けと学力/小宮山 博仁
今日もお読みいただき、ありがとうございました。
応援してくださる方はぜひ、Facebookページへ「いいね♪」をして頂けますと嬉しいです♪この数が小児がんのママたちを応援する数になっていきますように…♪
⇓ ⇓ ⇓
いいことさがそ~小児がんママと応援隊のコミュニティー~
Facebookページ https://www.facebook.com/iikotoouen
Facebookグループhttps://www.facebook.com/groups/iikotoouen/
(非公開グループです。小児がん関係者の方はもちろん<患児さん・ご家族・ナース・ドクター>以外の方からも、ぜひご意見いただけたらと思っております。お友だちになっていただけてからのご参加をお願いしています。)
- 2014/05/14 22:34 |
- ★保育・心理学・子育て(子ども/こころ), • 児童心理学 |